匠-長年焙煎している方へ
- 色々の経験・対応でデジタル計の導入を行い今の焙煎室に変更改造しました。
- 長年焙煎をやっていても火災が心配です、焙煎後燻っているのではないかと心配です。
- 焙煎機の改造。均一データー焙煎をお考えの参考になれば幸いです。
- 珈琲の業務に携わり珈琲の深さ、面白さ。結果利益の還元など人生の終わりまでに何か後継者に残したい、伝えたいと掲載しました。
大型焙煎機の改造
①~④の取付位置青字は取り付けた方が便利/赤字は必要
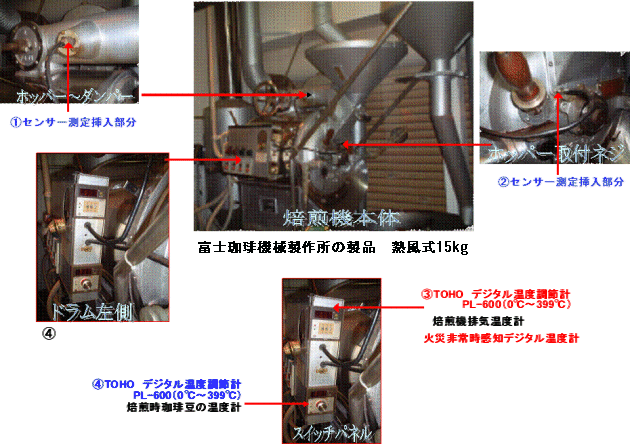
センサーの取付場所 温度計の働き①~④の説明
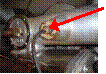
- 排気温度測定 購入時純正小型温度計が付いていた所にセンサーを差し込んであります。
- ダンパー開閉で温度変化します、その為排気の温度で有りデーターの作成及び焙煎の完了は目安。
- サイクロン・排気ファン・そこまでの煙突内で火が入ったときセット(300℃)感知します。「マッチ棒」が燃えている匂いがし、中でいぶっています。

- 焙煎時珈琲豆の温度 ホッパー結合部分のボルトを一本外しセンサへを挿入し珈琲豆に当たる用セット。
- 珈琲豆の正確な温度管理には最適な場所ですし、焙煎機にドリルで穴を開ける事も無いです。
- 他社の焙煎機及び釜の大きさで取り付けが変わりますが、センサーが豆に接触する場所で無いと意味が有りません。
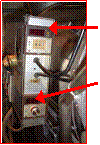
- 自作ボックスに各パーツを収納、配線コードはコイルチューブで保護。
- ①番のセンサーに接続されています、排気温度がデジタルで表示され、カウンターを300℃にセットし「火災時」赤い電球が点灯。 火が入り燻り始めると「マッチ棒を燃やした後の匂い」がし始める。対処方法は下の欄で記載。
- 通常は焙煎排気時の温度を表示
- ②番のセンサーに接続され、珈琲豆の温度がデジタルで表示、釜を暖め210℃に温度をセット、ブザーと電球で教えてくれる、生豆を投入。 ・投入後、最初ダイヤルを1パチに185℃セット達した所でダンパーを若干開き、次ぎに焙煎する豆をホッパーへ入れ、次に2パチ225℃~228℃の範囲で銘柄に合わせ落とす。 ダンパーはガスの炎の揺れを見て確認しますが、あまり回さない。
- 点検スプーンを出し入れすると釜の中に外気が入り込み温度で下ってしまいますので出来上り時に数回確認。 データーを作成すればスプーンは焙煎豆を出す数秒前のみの使用ですみます。
焙煎機の配線・スイッチ・ガス流量の接続


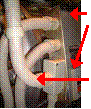
- 自作配線及びスイッチボックスに取付
- スイッチボックス内に電源のイン・アウトスイッチ及び照明を収納
- 上から焙煎機・冷却機の配線入力 真中 出力、200v電源入力(必ず手前に安全ブレーカーを取り付ける。下 各センサーの100v入力、出力。
- 配線時コード赤色、白、黒に注意、逆につなぐとモーターは反対に回転します。緑色はアースへ。
- 火災時の消化時の漏電・ショウト・コードの老化を防ぐため、カナフレットクス・カナフレキ・ミライPF管コネクターを取り付ける。
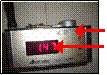
- 瞬間ガス流量計は下のガスメーターとセットになります。
- 過圧防止装置・圧力ゲージとは違いガスが流れている容量を正確にデジタルで瞬時表示。
- 15kgの釜で10kg焙煎時ガスの流量は1.35~1.40㎥/hで設定焙煎量を変えない場合は常に範囲内連続で焙煎。
- 3~5kgの少量の焙煎は1.1~1.0㎥/hで調整。但しmandheling・torajarインドネシア産。French Rostはガス量を下げ仕上げる。
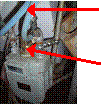
- ガスの元栓からインとアウトにガスホースをつなぐのみです。
- ガスメーターなので、そのつど使用量を数値で計測データー管理も出来ます。
- ⑤と⑥セットで100v電源が必要。
- センサー部分
焙煎機設置時の事前取付案、燻った時、火災の危険時の対応
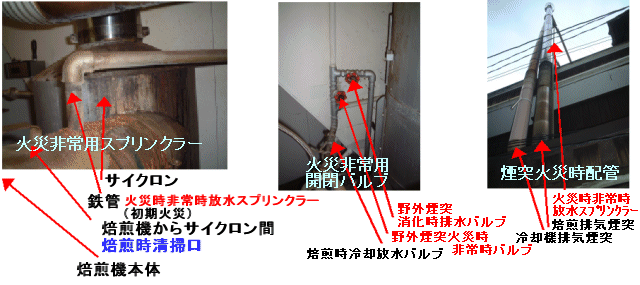

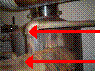
- 火災時、放水スプリンクラー「焙煎機ファンからサイクロンの間、この間で火が入った場合ストップバルブを開け消化する。焙煎中、焙煎後でもロースターは止めない。 (水道水がファンより焙煎機に逆流しない為)
- この部分の間が、一番引火の危険が有り焙煎後燻って居る危険性がある。温度が上昇すれば③が感知し知らせてくれる。
- 焙煎を行う前に必ず手前に作った清掃ふたよりスキン、焦げを取り去る。焙煎機清掃引き出しは焙煎三回に一回。
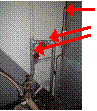
- 焙煎開始時はサイクロンのスプリンクラーはボールバルブT型を開ける。
- 2個のストップバルブは、上は排水用 下は給水用で使用後上のバルブは排水にしておき、⑨の焙煎用の煙突右「ステン」先端に鉄管で接続してある。取り付ける以前は、ここまで火が回ると中の細かい付着したゴミがただ燃え尽きるの待つだけで、煙突は真っ赤になり溶接部分が溶け出しました。
- 煙突の清掃もこまめに行いサイクロンの下の部分より煙が出てきたら限界のサインです。特に煙突のエビの所にスキンがたまり、ストレートの部分は、細かい綿状のゴミが付着し煙突の太さが細くなっているのに驚きます。二ヶ月に1回 。
- ただ煙突内部のエビの周りに付着した粘りの有る液状(コールタール状)は珈琲の香りのエキスの元が付いています。「採集方法、使い道検討中」
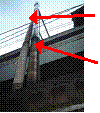
- 左側は冷却機用煙突で通常の焙煎では珈琲豆を落とした時のみ煙がでますが計の大きいサイズが良いです。 過去に経験した時、冷却機に落とした瞬間、焙煎豆が酸素と接触しすごい炎が上がり火災の危険性がありました。酸素の遮断、消化のみ。
- 3kgの釜では経験しました。この釜ではまだ経験していません。水槽の中に水を入れて置く事で、⑩の右の箱が対処してくれます。
- 右側焙煎用煙突には建物と接触している部分にグラスウールを巻いてあります。

- 写真左サイクロンから冷却シャワーの排水がでてきます。
- シルバースキンも一緒にながれてきます。以前はマタイ、カゴをサイクロン下に付けておきましたが、今は下水に垂れ流しです。
メンテナンス・冷却機の清掃
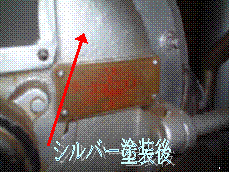
塗装後
当店セットしてから五回再塗装してあります。

耐熱スプレー シルバー

塗装後
下の部分は二回再塗装を行いました。以前は濃い緑色でした。
- 外せるパーツは取り外し内側の清掃もついでに、だいたいボルトを取れば外れますし構造も納得できて来ます。
- 特にダンパーは分解時に全開の位置、閉まる位置に記しを付けておくと便利です。
- 本体、ドラム等の分解はお薦めしません。
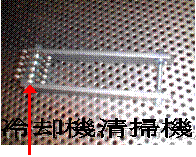
フジロイヤルパウチング五連
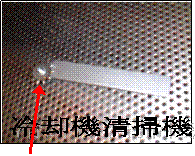
フジロイヤルパウチング一連
- 冷却が悪いと、結果的に焙煎度が進み別物に仕上がります。特に夏場は特にこまめに清掃。
- 五連と一連が有りますが、狭いすみは一連をお薦めします。
- 暗い時下の清掃口より懐中電灯で光を当てるとより良く確認できます。
- 定期的にこまめな清掃をお薦めします。
焙煎時の工夫・酸欠
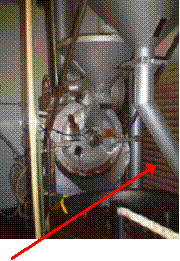
シャツター下ろしたとき
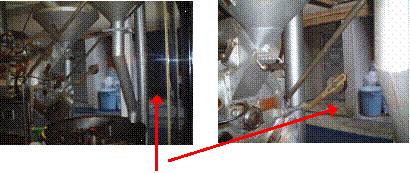
シャツター開けたとき
- 焙煎室の施工時にシャツターを取り付けました。新規の方は構造上難しい場合は出来る限り大きい窓を取り付けをお薦めします。
- 夏場は外の外気を取り入れ冷却を早めます。
- 外気の気温を考慮しシャツターの開閉位置を調整。
- 狭い焙煎室では酸欠の危険も有りますし。以前経験しました。夏場の長時間の焙煎はこたえます。
